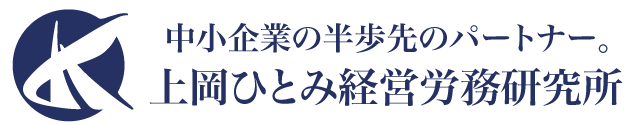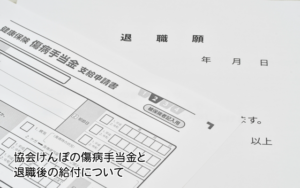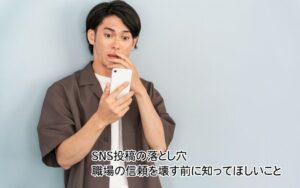【労務管理の落とし穴】有期雇用契約の終了で失敗しないための3つのチェックポイント
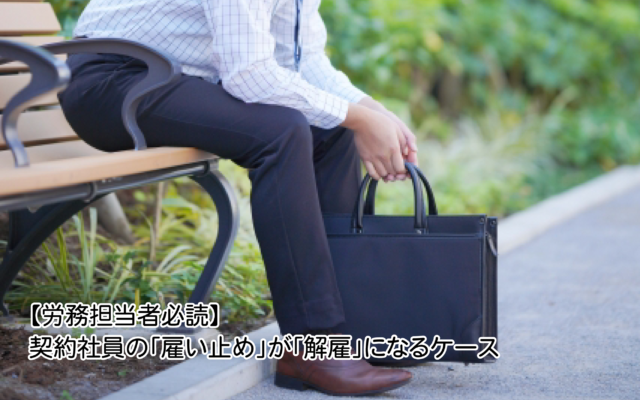
「期間満了だから」は危険?
有期雇用契約の終了「雇い止め」で押さえるべき法的論点とは?
有期雇用契約(契約社員、パートタイマーなど)は、「契約期間が決まっているから、期間が来れば自動的に終了できる」とお考えではないでしょうか。
実は、この認識には大きな落とし穴があります。
有期雇用契約の終了、いわゆる「雇い止め」は、無期雇用の「解雇」と同様に、法的に厳しく制限されるケースがあり、これを「雇い止め法理」と呼びます。単に「期間満了です」という通告だけで契約を終了させると、後々「雇い止めは無効だ!」として大きな紛争に発展するリスクを孕んでいます。
今回は、有期雇用契約を期間満了で終了させる際に、企業が確認すべき法的な論点を整理します。
論点1:その「雇い止め」は法的に有効か?
(労働契約法第19条)
「雇い止め法理」による無効化リスク
最も重要なのが「雇い止め法理」です。
以下の(1)または(2)に該当する場合、従業員からの契約更新の申し込みを、会社が「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」なく拒否することはできません。
これは実質的に、無期雇用の「解雇」とほぼ同じ厳しいハードルが課されることを意味します。
(1) 実質的に「無期雇用」と同じ状態(反復更新)
- これまでに何度も契約更新が繰り返されており、形式だけの契約更新に過ぎず、実質的には無期雇用と変わらない状態。
(2) 従業員が「更新を期待」する合理的な理由がある状態
- 従業員が「次の契約も当然更新されるだろう」と期待することに、客観的・合理的な理由がある場合。
「期待」の判断材料とは?
- 会社の言動
面談時や普段の業務中に、上司が「来年度もよろしく」「長く働いてほしい」など、更新を期待させる発言をしていないか。 - 更新の実態
同様の立場の他の契約社員が、これまで問題なく更新されてきた実績がないか。 - 業務の恒常性
担当している業務が、一時的なものではなく、恒常的に発生する業務ではないか。 - 更新手続き
契約更新の際に、面談や評価などの手続きが一切なく、事務的に(自動的に)更新されていないか。
これらの事情から「更新への合理的期待」があったと判断されると、「業績が悪化したから」「能力が期待通りでなかったから」といった曖昧な理由だけでは、「雇い止め」は無効となる可能性が高まります。
論点2:「無期転換ルール」を避けるための「雇い止め」ではないか?
(労働契約法第18条)
「無期転換ルール」回避と見なされることによる無効化リスク
有期雇用契約が更新されて通算5年を超えると、従業員には「無期雇用への転換申込権」が発生します(無期転換ルール)。このルールをよく理解している従業員は、「通算5年」が近づくと無期転換を申し出る準備をします。
ここで注意すべきは、「無期転換を申し込まれる前に、5年が経過する直前で契約を終了させよう」とするケースです。
無期転換ルールを意図的に回避するため(脱法目的)の雇い止めは、前述の「雇い止め法理」に照らし合わせた際に、「客観的に合理的な理由」を欠くと判断され、無効とされる可能性が極めて高いため、非常に危険です。
論点3:必要な「手続き」を踏んでいるか?
必要な「手続き」不備による法令違反リスク
仮に「雇い止め法理」に該当しない(=雇い止めが有効と認められる)ケースであっても、会社は以下の手続きを守る必要があります。
(1) 雇い止め予告(労働基準法)
- 以下のいずれかに該当する有期契約労働者を雇い止めする場合、会社は少なくとも30日前までに予告しなければなりません。
- 契約を3回以上更新している場合
- 1年を超えて継続勤務している場合
※あらかじめ「更新しない」と明示されている契約を除く
これは解雇予告と似ていますが、「雇い止」め独自のルールです。
(2) 雇い止めの「理由明示」
- 上記の(1)に該当する従業員を「雇い止め」する場合、会社は従業員から「雇い止めの理由」を求められたら、遅滞なく「理由証明書」を交付しなければなりません。
- そして、その理由は「契約期間が満了したから」という形式的なものではなく、「契約締結時に明示した、更新判断の基準(例:勤務成績の評価、事業の進捗状況など)に照らして、更新しない具体的な理由」を記載する必要があります。
まとめと実務上の対策
リスク回避の鍵は「雇入れ時」の入口管理と日頃の記録
有期雇用契約は、便利なようでいて、その「出口(終了時)」の管理が非常に難しい制度です。
「雇い止め法理」や「無期転換ルール」のリスクを回避するためには、入口である「雇入れ時」の管理が最も重要です。
(1) 契約書(労働条件通知書)の整備
- 契約更新の有無(自動更新にしない)
- 更新する場合の判断基準(例:勤務成績、会社の経営状況など)
- 担当業務(プロジェクトの終了とともに契約も終了するなど)
これらを曖昧にせず、明確に記載し、従業員に十分説明しておくことが、将来の「合理的期待」を防ぐ最大の防御策となります。
(2)日頃の言動管理
- 管理職が安易に「来年もよろしく」といった期待を持たせる言動をしないよう、社内教育を徹底する。
(3)更新手続きの厳格化
- 自動更新は絶対に避け、契約期間満了が近づくたびに必ず面談と評価を行い、「なぜ更新するのか(あるいは、しないのか)」を記録に残す。
有期雇用の終了は、手続きが複雑で法的な落とし穴が潜んでいます 。少しでもご不安な点がございましたら、トラブルを未然に防ぐためにも、当事務所へご相談ください。