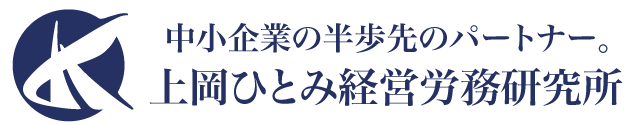【義務化】2025年6月1日施行!職場での熱中症対策、何が変わる?
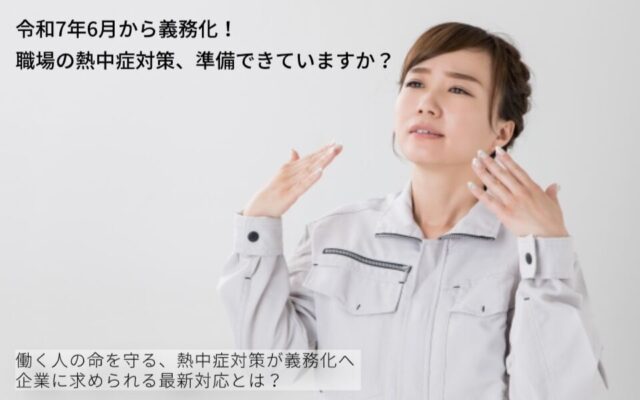
職場での熱中症対策が義務化!笹川工務店が専門家に聞く最新対策とは
令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます
登場人物紹介
- 笹川社長(31歳):工務店三代目。アパレル、雑貨、飲食と新事業を展開するやり手だが、神経質でお腹を壊しやすい
- 佐藤常務(58歳):先々代から笹川工務店を支える大番頭。経理のエキスパート
- 上岡ひとみ社労士:開業21年のベテラン社労士。230社の顧問先を持つ
令和7年6月1日から施行される労働安全衛生規則の改正により、職場での熱中症対策が義務化されます。具体的な対策をどう進めていけば良いかわからないという中小企業や事業主も少なくありません。義務化される内容と実践的な対応方法を分かりやすく解説します。
夏の現場、新たな義務が始まる
 笹川社長
笹川社長笹川社長:
「佐藤さん、また法改正ですか?最近、法律がコロコロ変わって、お腹が痛くなりそうです…」
 佐藤常務
佐藤常務佐藤常務:
「社長、今度は熱中症対策の義務化ですよ。建設現場を抱える我々には重要な話です」
 上岡社労士
上岡社労士上岡社労士:
「そうなんです。令和7年6月1日から、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業には新しい対応が必要になります」
 笹川社長
笹川社長「WBGT値?何ですか、それ?」
WBGT値って何?
WBGT値は、熱中症予防を目的とした指標です。熱中症は屋外だけでなく、屋内でも発生するため、気温だけでなく、これらの要素も考慮して算出されます。これにより、屋内外を問わず、人体が感じる暑さをより正確に評価することができます。
 上岡社労士
上岡社労士「WBGT値は『暑さ指数』のことで、気温だけでなく湿度や日射も考慮した熱中症リスクの指標です。簡単に言うと、『体感的な暑さ』を数値化したものですね」
 佐藤常務
佐藤常務「なるほど。気温だけじゃダメなんですね」
 上岡社労士
上岡社労士「はい。例えば同じ気温30度でも、湿度が高い日と低い日では体への負担が全然違いますよね。WBGT値ならそれが分かります」
| 身体作業強度 | WBGT基準値(暑さ指数) |
| 安静・軽い手作業 | 33°C |
| 軽い手作業・歩行など | 30°C |
| 継続的な手足の作業 | 28°C |
| 重機操作・金属物の運搬 | 26°C |
| 激しい運動・重労働 | 25°C |
新制度の核心は「見つける・判断する・対処する」
「見つける・判断する・対処する」この3つのステップは、熱中症による死亡災害の主な原因とされる「発見の遅れ」と「異常時の対応不備」をなくすためのものです。重篤化を防ぎ、死亡災害を未然に防ぐ、これらの基本的な行動が、実はできていないケースが多いのです。
 笹川社長
笹川社長「具体的に何をすればいいんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「基本は3ステップです。まず『見つける』- 作業員の様子を観察する。次に『判断する』- 医療機関への搬送や救急隊要請が必要か判断する。最後に『対処する』- 適切な処置を行う、という流れです」
 佐藤常務
佐藤常務「当たり前のことのように聞こえますが…」
 上岡社労士
上岡社労士「そうなんです。でも実際の現場では、この当たり前のことができていないケースが多いんです。厚生労働省の分析では、熱中症による死亡災害の100件中78件が『発見の遅れ』、41件が『異常時の対応不備』が原因でした」
事業者に義務付けられる具体的な対応
事業者は、熱中症の兆候がある作業員を速やかに把握するための報告・連絡体制を整備し、従業員に周知することが義務付けられます。さらに、熱中症が疑われる労働者が発生した場合に備え、搬送先の医療機関や緊急連絡網など、迅速かつ的確な対応を可能にする緊急時対応体制の準備も求められます。
 笹川社長
笹川社長「義務って、具体的に何をしなければならないんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「主に2つの体制整備が必要です」
1. 報告・連絡体制の整備
 上岡社労士
上岡社労士「まず、熱中症の自覚症状がある作業者や、熱中症のおそれがある作業者を見つけた人が、その旨を報告するための体制整備と関係作業者への周知が必要です」
 佐藤常務
佐藤常務「現場から事務所への連絡体制ということですね」
 上岡社労士
上岡社労士「そうです。ただし、単に連絡先を決めるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイスの活用など、積極的に把握する努力も求められています」
2. 緊急時対応体制の準備
 上岡社労士
上岡社労士「次に、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合の迅速かつ的確な判断が可能となるよう、以下の準備が必要です」
準備する内容
- 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
- 作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等による重篤化防止のための必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知
現場での実践的な対応フロー
熱中症が疑われる作業員を発見した場合の、具体的な行動手順をフローチャート形式で分かりやすく示しています。このフローに沿って行動することで、初期対応の遅れを防ぎ、熱中症による健康被害を最小限に抑えることができます。
 笹川社長
笹川社長「実際に熱中症の疑いがある人を見つけたら、どうすればいいんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「フローチャートで説明しますね」
1.熱中症のおそれのある者を発見
2.作業離脱・身体冷却
異常あり → 救急隊要請
異常なし → 自力での水分摂取可能か確認
3.意識状態の確認
4.水分摂取ができる場合 → 経過観察
5.水分摂取ができない場合 → 医療機関への搬送
 佐藤常務
佐藤常務「意識があっても、水が飲めなければ病院送りなんですね」
 上岡社労士
上岡社労士「その通りです。そして重要なのは、回復後も体調急変の可能性があるため、連絡体制や体調急変時の対応をあらかじめ定めておくことです」
「いつもと違う」サインを見逃すな
普段から熱中症の初期症状を把握しておけば、「手足がつる」「立ちくらみがする」「いつもと汗のかき方が違う」といった些細な変化をいち早く察知できます。これにより、熱中症が疑われると迅速に判断できるため、重篤化する前に適切な応急処置や医療機関への搬送を行うことが可能になります。
 笹川社長
笹川社長「熱中症って、どんな症状が出るんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「初期症状は意外と気づきにくいものが多いんです」
症状例
- あれっ、何かおかしい
- 手足がつる
- 立ちくらみ・めまい
- 吐き気
- 汗のかき方がおかしい(汗が止まらない/汗が出ない)
- あの人、ちょっとヘン
- イライラしている
- フラフラしている
- 呼びかけに反応しない
- ボーッとしている
 上岡社労士
上岡社労士「『何となく体調が悪い』『すぐに疲れる』なども初期症状です。周囲の人が『いつもと違う』と感じたら、すぐに周囲の人や現場管理者に申し出ることが大切です」
手順や連絡体制の整備例
熱中症対策を実効性のあるものにするため、熱中症が発生した際の初期対応の手順や、緊急連絡先などの具体的な情報を、従業員全員で共有し、いつでも確認できるようにしておくことが大事です。
 佐藤常務
佐藤常務「具体的にはどんな体制を作ればいいんでしょうか?」
 上岡社労士
上岡社労士「いくつかの方法があります」
朝礼やミーティングでの周知
「安全掲示板や朝礼で、WBGT値や注意事項を共有する方法です」
会議室や休憩所での掲示
「見やすい場所に熱中症対策の手順を掲示しておきます」
メールやイントラネットでの通知
「例えば『件名:本日はWBGT値が28℃を超える見込みです』といった注意喚起メールを送信する方法もあります」
まとめ:準備は今から始めよう
 笹川社長
笹川社長「うちの現場でも、すぐに準備を始めないといけませんね」
 佐藤常務
佐藤常務「そうですね。特に夏の現場作業が多い我々には重要な対策です」
 上岡社労士
上岡社労士「施行は令和7年6月1日ですが、準備に時間がかかりますから、今から体制づくりを始めることをお勧めします。WBGT値の測定器具の準備、緊急連絡網の整備、従業員への教育など、やることはたくさんありますよ」
 笹川社長
笹川社長「分かりました。佐藤さん、来週までに現状の整理をお願いします。従業員の安全が第一ですからね」
 佐藤常務
佐藤常務「承知いたしました。上岡先生、継続的にご相談させていただけますか?」
 上岡社労士
上岡社労士「もちろんです。熱中症対策は一度作って終わりではなく、継続的な見直しと改善が必要です。一緒に働く人みんなが安全に働ける環境を作っていきましょう」
【ポイント】
- 令和7年6月1日から熱中症対策が義務化
- WBGT値28度以上または気温31度以上での長時間作業が対象
- 「見つける・判断する・対処する」の3ステップが基本
- 報告・連絡体制と緊急時対応体制の整備が必須
- 「いつもと違う」サインを見逃さない観察力が重要
当事務所では、熱中症対策義務化に対するご相談に対応しております。お気軽にご相談ください