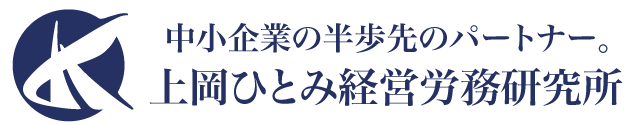協会けんぽの傷病手当金と退職後の給付について
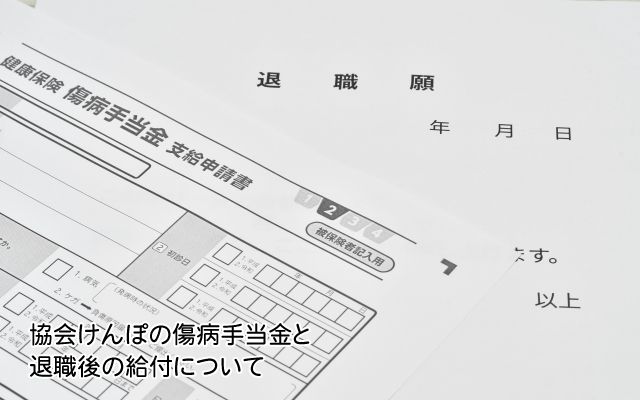
傷病手当金とは
傷病手当金は、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与を受けられない場合に支給される制度です。病気やケガで働けなくなった際の生活を保障する、重要なセーフティネットとなっています。
傷病手当金の基本的な支給要件
傷病手当金が支給されるには、次の条件を満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガによる療養のため仕事に就くことができないこと
- 連続して3日間会社を休んだ後、4日目以降も休んでいること(最初の3日間は「待期」と呼ばれます)
- 休んだ期間について給与の支払いがないこと
支給される金額
1日あたりの支給額は、以下の計算式で算出されます。
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷ 30日 × 2/3
例えば、平均標準報酬月額が30万円の場合、1日あたり約6,667円が支給されます。
支給期間
支給開始日から通算して1年6ヵ月まで支給されます。令和4年1月より、途中で仕事に復帰した期間があっても、通算で1年6ヵ月受給できるようになりました。
退職後の傷病手当金について
ここからは、多くの方が気になる「退職後も傷病手当金を受け取れるのか」について詳しく解説します。
退職後も継続して受給できる3つの条件
退職後も傷病手当金を継続して受給するには、以下のすべての条件を満たす必要があります。一つでも欠けると、退職後の給付は受けられません。
条件① 被保険者期間が継続して1年以上あること
退職日までに、協会けんぽの被保険者として継続して1年以上加入している必要があります。
注意点:
- 任意継続被保険者や国民健康保険の加入期間は含まれません
- 健康保険組合から協会けんぽへの切り替えがあった場合でも、1日も空くことなく連続していれば通算できます
条件② 退職日の前日までに連続3日以上出勤せず、退職日も出勤していないこと
これは非常に重要なポイントです。退職日当日に出勤してしまうと、この条件を満たさず、退職後の傷病手当金は受給できなくなります。
具体例:
- ○ 退職日前から継続して休んでおり、退職日も休んでいる → 条件を満たす
- × 退職日に挨拶のため出勤した → 条件を満たさない(退職後の給付なし)
退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日は、医師が労務不能と認めた期間である必要があります。
条件③ 退職日に受給していた傷病で引き続き労務不能であること
退職前から受給していた同じ病気やケガで、引き続き働けない状態が続いている必要があります。
注意点:
- 退職後にまったく別の病気やケガで申請しても、その傷病については支給されません
- 在職中にすでに傷病手当金を受給している必要があります
退職後の傷病手当金で注意すべきポイント
支給期間は変わらない
退職後も、支給開始日から通算1年6ヵ月という期間は変わりません。退職したからといって期間が延びるわけではありません。
任意継続被保険者は対象外
退職後に任意継続被保険者になった場合、新たに傷病手当金を受給することはできません。ただし、在職中から継続して受給している場合は、要件を満たせば継続して受給可能です。
申請先は在職時の加入支部
退職後も、申請書の提出先は在職時に加入していた協会けんぽの支部となります。退職後に任意継続に加入した場合でも、傷病手当金の申請は在職時の支部に行います。
被保険者証の記号番号は退職前に必ず控えておきましょう。
退職後に金額が調整されるケース
退職後の傷病手当金は、以下の場合に金額が調整されます。
老齢退職年金を受給している場合
老齢年金を受給している場合、傷病手当金は支給されないのが原則です。ただし、老齢年金の日額(年金額÷360)が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
具体例:
- 傷病手当金の日額:7,000円
- 老齢年金の日額:5,000円(年金額180万円÷360日)
- 支給される傷病手当金:2,000円(差額)
その他の調整対象
- 給与・手当が支給されている場合
- 同じ傷病で障害厚生年金または障害手当金を受けている場合
- 労災保険から休業補償給付を受けている場合
- 出産手当金を受けている場合
これらの給付の日額が傷病手当金の日額以上の場合、傷病手当金は支給されません。日額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
失業給付との関係
傷病手当金と雇用保険の失業給付(基本手当)は、同時に受給することはできません。
- 傷病手当金: 病気やケガで働けない人への給付
- 失業給付: 働くことができ、就職活動をしている人への給付
労務不能期間中の失業給付については、管轄のハローワークに確認することをおすすめします。
まとめ
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった時の大切な保障制度です。特に退職後も継続して受給できることは、療養に専念するための重要な支えとなります。 ただし、退職後の継続給付には厳格な要件があり、特に退職日に出勤しないことは非常に重要です。詳しくはご相談ください