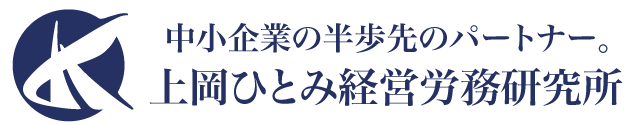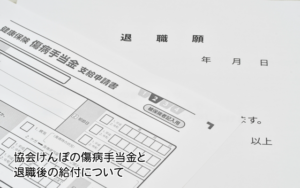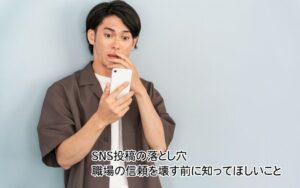「解雇」と「退職勧奨」は全くの別物!知っておきたい法律上の大きな違い
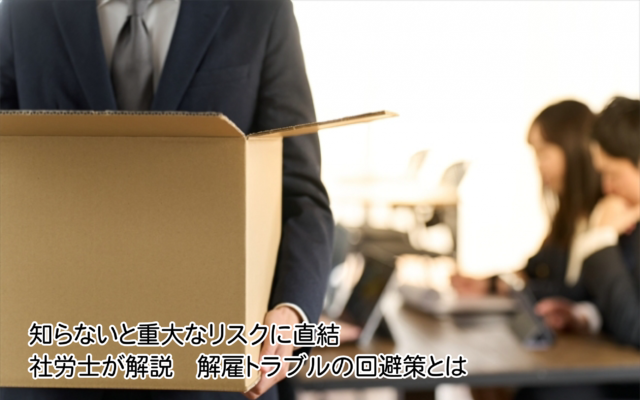
「あの従業員に辞めてもらいたい」と考えたとき、対応策として「解雇」や「退職勧奨」が選択肢として頭に浮かぶことでしょう。
実際には、法的リスクの低い「退職勧奨」から進め、合意に至らなければ…「解雇」を検討するといった対応として捉えられがちです。
しかし、この二つは、法的な意味合い、手続き、そして会社が負うリスクにおいて、全くの別物です。その明確な違いや法律上の厳格なルールを正しく理解せず、曖昧なまま進めてしまうと、「不当解雇」や「退職強要」として、深刻な労務トラブルに発展する可能性があります。
経営者・人事担当者として必ず押さえておくべき、両者の決定的な違いと実務上の注意点を解説します。
1.「解雇」とは? ― 会社による一方的な契約終了
「解雇」とは、会社が従業員の意思に関わらず、一方的に労働契約を終了させることを指します。
従業員側に「辞めたくありません」という意思があっても、会社側が「辞めてください」と通告し、契約を打ち切る行為です。
解雇の厳格な成立要件
従業員の生活基盤を一方的に奪う行為であるため、法律(労働契約法第16条)によって厳しく制限されています。これを「解雇権濫用(らんよう)の法理」と呼びます。
「解雇」が法的に有効と認められるには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要です。簡単に言えば、「誰が見ても辞めてもらうのが当然だ」という、よほどの理由がなければ、その解雇は「不当解雇」として無効になります。
解雇予告手当が必要
「解雇」を行う場合、原則として30日以上前に予告するか、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。
リスク
要件を満たさない「解雇」は「不当解雇」として無効となり、従業員から地位の確認(復職)や、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払いを求められるリスクがあります。
2.「退職勧奨」とは? ― 従業員の合意に基づく契約終了
「退職勧奨」(たいしょくかんしょう)とは、会社が従業員に対して「辞めてほしい」と伝え、従業員の合意を得て労働契約を終了させる(合意退職する)ための働きかけを指します 。
これは、会社による一方的な決定ではなく、最終的に退職するかどうかを決めるのは従業員本人です。あくまで従業員本人の意思によって退職が成立するケースです。
合意退職における従業員の「拒否権」
最大のポイントは、従業員には「退職勧奨」を「拒否する自由」があることです。従業員が「辞めません」と明確に意思表示した場合、会社はそれ以上退職を強要することはできません。
解雇予告手当は不要
「退職勧奨」は「解雇」ではないため、解雇予告や解雇予告手当の支払いは法律上不要です。
ただし、従業員に合意してもらうためのインセンティブとして、会社側が任意で「退職金の上乗せ」、「特別功労金」、「有給休暇の全消化」といった「優遇措置(退職条件)」を提示することが一般的です。
リスク
説得活動が行き過ぎると、「退職強要」という違法行為(不法行為)とみなされ、従業員から損害賠償(慰謝料)を請求されるリスクがあります。
3.「解雇」と「退職勧奨」の決定的な違い(比較表)
法的性質・リスク・手続きを徹底比較、両者の違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 解雇 | 退職勧奨(が成立した場合) |
|---|---|---|
| 従業員の合意 | 不要(会社からの一方的通告) | 必要(合意退職が成立条件) |
| 法的性質 | 労働契約の一方的な解約 | 労働契約の合意解約 |
| 解雇予告手当 | 原則必要 | 不要 |
| 主な法的リスク | 不当解雇(解雇が無効になる) | 退職強要(損害賠償責任) |
| 根拠となる法律 | 労働契約法、労働基準法 | 民法(契約の合意) |
4.実務上の最重要注意点:「退職勧奨」が「退職強要」になる境界線
退職勧奨は、進め方を一歩間違えると「従業員の自由な意思決定を妨げた」として、違法な「退職強要」と判断されます。その違法となる「境界」についてご説明いたします。
過去の裁判例では、以下のような行為が違法な退職強要にあたるとされています。
執拗(しつよう)な説得
- 従業員が明確に「辞めません」と拒否しているにもかかわらず、何度も面談を繰り返す。
(例:数ヶ月にわたり数十回実施)
長時間・威圧的な面談
- 1回の面談が数時間におよぶ。
- 大声で怒鳴る、机を叩く、侮辱的な言葉を浴びせる。
脅迫・虚偽の説明
- 「辞めなければ懲戒解雇にするぞ」(実際には懲戒事由がないにも関わらず)と脅す。
- 「応じなければ給料を下げる」「別の部署に飛ばす」など、不利益な取り扱いをほのめかす。
退職に追い込む嫌がらせ
- 仕事を一切与えない、無視する、隔離された席に移動させるなど、自主退職に追い込むための環境を作る。
5.まとめ:トラブル防止のために
「解雇」と「退職勧奨」は、似ているようで全く異なる法的手続きです。
- 「解雇」は、法的なハードルが極めて高く、会社にとって最大のリスクとなり得ます。
- 「退職勧奨」は、円満な合意退職を目指す有効な手段ですが、その進め方には細心の注意が必要です。
退職勧奨が成立した場合は、口約束で終わらせず、退職条件(退職日、上乗せ金の有無や金額など)を明記した「退職合意書」を必ず書面で取り交わし、労使双方の合意の証拠を残すことが、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。
従業員の退職に関する対応は、一歩間違えると法的な紛争に直結します。判断に迷った場合は、実行に移す前に、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。