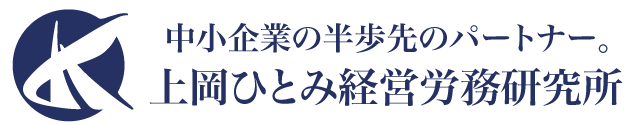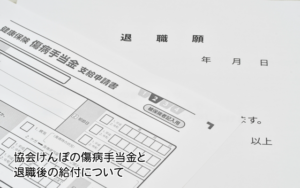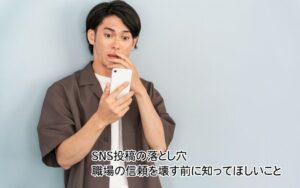「論語と算盤」~渋沢栄一が説いた、道徳と経済の一致~
【生きるに値する社会とは】理念と利益を両立する経営の羅針盤
「論語と算盤」――渋沢栄一が説いた、道徳と経済の一致。
今の時代こそ、この考え方が必要です。
ただ儲ければいい。効率化すればいい。そんなビジネスは、もう限界にきています。
人としての志を持ち、誰かの役に立ちたいと願いながら働くこと。
その先にこそ、本当のやりがいや幸福があるのではないでしょうか。
ビジネスは社会を変える力があります。
一人ひとりが、小さくても“誰かのため”を起点に動き出せば、社会は確実に変わります。利益も出す。でも、その前に「何のために?」を問い続ける。そんな企業や人が増えていくことが、誰もが“生きるに値する社会”をつくる第一歩だと思うのです。
限界に来ている「儲け第一主義」の末路
短期的な利益を最優先する経営は、もはや持続可能性を失いつつあります。
- 失われる信頼
不祥事や隠蔽体質が露見し、一度失った社会からの信頼を取り戻すことは至難の業です。 - 高まる離職率
「何のために働いているのか」を見失った社員は、高い給与だけでは留まりません。特にミレニアル世代以降は、企業の存在意義(パーパス)に共感できるかを重視します。 - 顧客の視点の変化
消費者は、単に安くて便利な商品を選ぶのではなく、「どんな企業が作っているのか」「社会に良い影響を与えているのか」という視点で購買行動を決めるようになっています。
こうした背景から、現代の経営トレンドである「SDGs」「ESG投資」といった概念は、実は渋沢栄一が100年前に説いた「道徳経済合一説」の現代版にほかなりません。道徳(社会貢献)なき経済は砂上の楼閣であり、経済(利益)なき道徳は単なるお題目でしかないのです。
「何のために?」が利益を生むパーパス経営の力
では、理念(道徳)と利益(算盤)を両立させるには、具体的にどうすれば良いのでしょうか。鍵は、「何のために?」という問いを経営の羅針盤に据えることです。
この問いを突き詰めることで、企業には3つの大きなメリットが生まれます。
- 採用力・定着率の向上
企業が掲げる「何のために」に共感した人材が集まり、困難な状況でも目的を共有して前向きに取り組めるチームが形成されます。 - ブレない意思決定
コスト削減か、顧客満足か、といった二項対立に陥ったときも、パーパスに照らし合わせることで、長期的な利益に繋がる正しい判断を下せるようになります。 - イノベーションの促進
「誰かの役に立ちたい」という内発的な動機こそが、既存の枠を超えた新しい商品やサービスを生み出すエネルギーとなります。
例えば、当社の顧問先企業では、理念を共有してから社内の風通しが劇的に改善し、それまで誰も見向きもしなかった社員の提案が、新しい事業の柱になった例もあります。
今、貴社が取り組むべき「生きるに値する経営」への第一歩
理念と利益を両立させる「生きるに値する経営」は、決して特別な大企業だけのものではありません。
貴社が今日から取り組める第一歩は、「理念の言語化と浸透」です。
- ステップ1:存在意義(パーパス)の再定義
貴社は「誰のために」「どんな価値」を提供しているのかを、利益目標の前に徹底的に問い直し、社員全員が共感できる言葉で明確に定義します。 - ステップ2:日々の業務への落とし込み
定義した理念を、単なる額縁の言葉にせず、人事評価制度や日々の行動指針に結びつけます。すべての意思決定を「私たちのパーパスに合致しているか?」という視点でチェックする習慣をつけましょう。
貴社の「何のために?」を具現化しませんか?
利益を出しながら、同時に社会に貢献する。 社員がやりがいを感じ、お客様に心から感謝される。 そんな「生きるに値する経営」は、理想論ではありません。
貴社の「何のために?」を問い直し、渋沢栄一の思想を現代のビジネスに活かす具体的な戦略と仕組みづくりについて、ぜひ一度、私たちにお話をお聞かせください。
最後に…
硬い話ばかりになりましたが、当社の顧問先企業にも、社員の皆さんの癒やしとなっているカメレオンの『レオンちゃん』(オス)がいます。理念を持つ経営は、働く人たちの心に余裕を生み、職場の雰囲気さえも明るくする、という一例かもしれません。