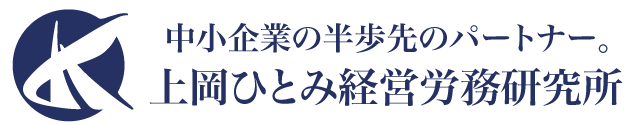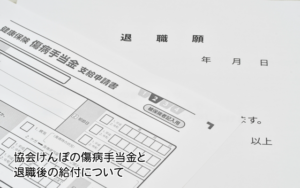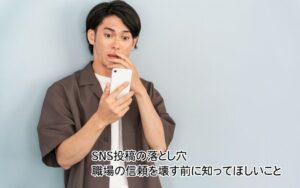日本発信の経済論~松下幸之助先生に学ぶ「ことから人へ」~
予言された日本の危機
松下幸之助氏は、今から60年以上も前の1960年代初頭という、日本が高度経済成長の只中にあった時代から、一つの警鐘を鳴らしていました。
それは、「今のままの、日本の『心の在り方』では、繁栄は続かず、いずれ(1980年代に)日本に、経済危機が訪れる」という、非常に具体的な予言でした。
松下氏が危惧したのは、経済成長そのものではありません。物質的な豊かさや経済効率が最優先され、その活動を支えるべき「人」の精神性や人間性が置き去りにされてしまう社会構造です。この「物中心の考え方」の行き着く先こそが、社会の歪みと停滞であると見抜いていたのです。
「支配の物語」の限界
そして今、私たちはまさにその予言の延長線上にいます。
「モノ(こと) 」や経済効率が最優先され、働く「人」が置き去りにされてきた物語(私がここで言う「支配の物語」)は、もはや限界を迎えています。成果主義の行き詰まり、職場でのエンゲージメントの低下、企業と社会との乖離など、多くの人がこの物語に疑問を感じています。
今こそ、価値観を「ことから心に」転換すべき時です。
組織を動かす「心の働き」という力
松下幸之助氏が、危機を乗り越える力として重視したのが「心の働き」です。
それは「共感」「利他」「信頼」という、人間としての根源的な力です。
お金や権力による支配構造が、短期的な効率しかもたらさなかったのに対し、この「心の働き」こそが、企業と従業員、そして社会との間に、持続的な価値を生み出す唯一の力だと私は思います。
「心の働き」
- 「共感」
真のニーズを発見し、イノベーションの土壌となります。 - 「利他」
利潤を社会への貢献の証と捉える「水道哲学」に通じ、企業活動を永続させる大義となります。 - 「信頼」
は、多様な個性が最大限の力を発揮できる安全な組織基盤となります。
新しい組織論・経済論への転換
これまでの「もの・こと・成長」とは違う、自然と共生し、多様性を認める日本の精神。これは、世界が陥った「支配」のゲームに対する、日本からの「新しい組織論・経済論」の提言です。
テクノロジーが進化し、効率化の追求が極限に達する「今だからこそ」、機械には代替できない、経営者と職員さんの「在り方」が未来を決めます。
時代の大転換期、会社の在り方、組織の在り方、すべてを見直さないといけない時代に入っていることを強く感じます。
次の一歩を踏み出すために
松下氏が予言した危機を乗り越え、企業が真の活力を取り戻すには、この「心の働き」を、単なる精神論で終わらせず、組織の仕組みや経営戦略の中核に据える必要があります。
しかし、長年培われた「こと・モノ中心」の組織設計を、「人・心中心」へと転換することは、理念の再構築や評価制度の抜本的な見直しを伴う、容易ではない課題です。
この時代の大転換期における、「ことから人へ」の組織デザインや、経営者・リーダーの「在り方」の見直しについて、具体的なソリューションをお求めでしたら、弊所にて専門的なご相談を承っております。