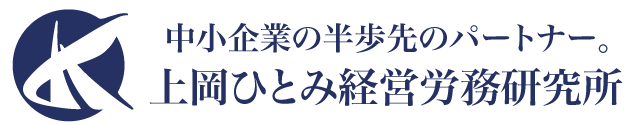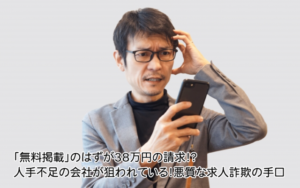【社労士が見た】失われた「繋がり」の代償。疲弊する労働現場のリアル

かつての日本社会は、村落共同体(ムラ)や家族制度(イエ)、地域コミュニティなど、様々な「共同体」によって支えられてきました。これらの共同体は相互扶助の仕組みを提供し、個人のアイデンティティを形成する基盤となっていました。 鹿児島の郷中教育もその大切な一つです。
変容する「共同体」とその影響
しかし現代社会では、都市化や核家族化、デジタル化の進展により、従来の共同体は大きく変容しています。特に注目すべきは「会社共同体」の変化です。終身雇用や年功序列に代表される日本型経営は、働く人々に安定と帰属意識を与える共同体として機能してきました。
労働現場で顕在化する「繋がり」の喪失
社会保険労務士として労働現場を見ていると、この会社共同体の弱まりが多くの問題の根底にあると感じます。パワーハラスメントの増加は上下関係の変化と権威の揺らぎを、メンタルヘルス不調の広がりは帰属意識の欠如を反映しています。また、世代間の価値観の相違によるコミュニケーション不全も、共通言語や暗黙の了解が失われつつある証左と言えるでしょう。
現代社会に適した共同体のあり方を模索する
これからの時代に必要なのは、個人の自律と多様性を尊重しながらも、新たな形での繋がりや相互理解を深める環境づくりです。単なる懐古主義ではなく、現代社会に適した共同体のあり方を模索することが、労働現場を含めた、社会全体の課題解決への一歩となるのではないでしょうか。
写真は、鹿児島県指宿市開聞地区・薩摩国一之宮 枚聞神社 勅使殿と長庁

「失われた繋がり」がもたらす課題は、決して他人事ではありません。もし貴社でも同様の課題を感じたら、今すぐご相談ください。