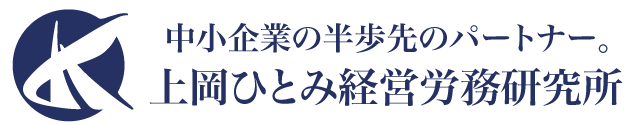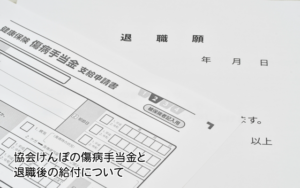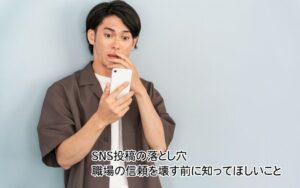【中小企業向け解説】男性育休取得の義務化は違法?50~100人規模企業の育児休業対応法

中小企業の人事担当者必見!50~100人規模の会社で男性育休をどう進める?育児休業は強制できる?法的根拠と実務上のリスク、中小企業にも実践可能な育休取得率向上策を解説。育児・介護休業法の正しい理解で法的トラブルを避ける方法をご紹介。
50~100人規模の中小企業の人事担当者なら、こんな悩みを抱えていませんか?
✓ 「男性育休の取得促進が求められているけど、少人数の会社でどう対応すればいい?」
✓ 「取りたくない社員に育休を強制してもいいの?」
✓ 「限られたリソースでどこまで育休支援ができる?」
近年、男性の育児休業取得促進が社会的に注目され、特に2022年の「産後パパ育休」制度開始以降、中小企業にも男性社員の育休取得率向上が求められています。2024年2月時点では、「従業員100人超の企業に対し、男性の育休取得率の目標値設定と公表を義務付ける方針」との報道もなされており、50~100人規模の企業も対応が必要です。
しかし、大企業と違って人員に余裕がない中小企業では、取得率向上を目指すあまり強制に走ってしまうと、法的リスクを招く恐れがあります。本稿では、育児休業の法的性質を踏まえながら、50~100人規模の企業が実践できる現実的な対応策をご紹介します。
中小企業でも知っておくべき育児休業の法的性質
まず押さえておきたいのは、育児休業の法的な位置づけです。企業規模に関わらず適用される重要な法的知識です。
育児・介護休業法では、労働者が法定の要件を満たして申し出をした場合、事業主はこれを拒否できないとされています(育児休業は同法6条1項、出生時育児休業は同法9条の3第1項)。
つまり、育児休業は労働者の権利として保障されているのであって、義務ではありません。法律用語では「形成権」と呼ばれ、権利者の一方的意思表示によって休業という効果を発生させる権利です。水町勇一郎教授の『詳解 労働法 第3版』(東京大学出版会)でもこの点が明確に述べられています。
権利である以上、その行使は権利者の自由意思に委ねられるもの。取得するかしないかは、最終的には労働者自身が決められるものなのです。
中小企業での男性育休取得強制はリスクあり!法的問題点
「うちの会社、男性育休100%取得を実現したい」と考える経営者や人事担当者もいるかもしれません。しかし、強制することには法的リスクがあります。
育児・介護休業法の規制範囲
育児・介護休業法では、育児休業の申し出をしたことなどを理由とする不利益取扱いは禁止されていますが(育介法10条、同法施行規則22条の2)、「育児休業をしなかったこと」を理由とする不利益取扱いについては直接規制していません。
しかし、だからといって育休取得を強制しても大丈夫、という話にはなりません。
私法上の権利侵害の問題
育児休業は労働者の権利であり、権利の行使を強制すること(「育休を取らないなら評価を下げる」など)は、権利者の自由を侵害する行為として違法となる可能性があります。
実際の裁判例でも、育児休業の申し出を拒否された労働者の権利侵害が認められた例があります(日欧産業協力センター事件 東京高裁 平17.1.26判決)。これは権利行使の妨害が違法になることを示していますが、同じ論理で「権利を行使しない自由」を侵害することも違法になり得るのです。
中小企業は大企業に比べて訴訟リスクへの備えが十分でない場合が多いため、こうした法的リスクには特に注意が必要です。
50~100人規模企業でも実践できる!男性育休推進4つの戦略
では、限られたリソースの中で、男性育休の促進と従業員の権利尊重をどう両立させればよいのでしょうか?50~100人規模の企業でも実践できる具体策をご紹介します。
1. 少人数企業でも実現できる育休取得環境づくり
まず最も重要なのは、「取りたい人が躊躇なく取れる環境」を整えることです。大企業のような充実した制度がなくても、50~100人規模の企業で実現可能な施策があります:
- 育児休業制度の分かりやすいガイドブック作成(1枚でも可)(育介法21条の努力義務)
- 業務の「見える化」と「多能工化」で少人数でもカバーできる体制構築
- 管理職への育休制度研修(育介法22条の職場理解増進措置)
- 中小企業向け両立支援助成金の活用(厚生労働省の助成金)
実例:従業員80名のA社(製造業)では、部署ごとの業務手順書作成と相互研修で「誰でも代替可能」な体制を構築。人員に余裕がなくても育休取得を実現しています。
2. 中小企業向け「育児参画」の多様な選択肢
育児へのかかわりは、育休取得だけが唯一の方法ではありません。特に中小企業では、フレキシブルな対応が可能という強みがあります:
- 時短勤務や時差出勤の柔軟な運用(育介法23条)
- 社長の理解を得た上での在宅勤務や柔軟な働き方の導入
- 子どもの行事参加のための優先的な有給休暇付与
- 「育児特別休暇」など短期休暇制度の新設(取得しやすい短期間の設定)
実例:従業員120名のB社(小売業)では「男性育児参画プログラム」として、育休以外にも「育児時間確保制度」(週2回の早退OK)など、中小企業だからこそできる柔軟な制度を用意。
3. 中小企業に適した目標設定と評価の工夫
取得率100%という高すぎる目標設定は、中小企業では現実的でない場合もあります。自社の規模や状況に合った目標設定を:
- 段階的な目標設定(初年度30%→50%→70%と段階的に)
- 「男性育休取得率」と「育児参画率」の複合指標の設定
- 取得日数に応じた複数のオプション提示(5日、2週間、1か月など)
実例:従業員90名のC社(サービス業)では、「男性育休・5日間チャレンジ」という短期間の取得を推奨する仕組みを導入。まずは短期間から始め、徐々に取得日数を増やしていく方針で、初年度から60%の取得率を達成しました。
4. 50~100人規模企業ならではの「顔の見える」コミュニケーション
中小企業の強みは、社員同士の距離が近く、個別のコミュニケーションがとりやすいこと。この強みを生かした施策を:
- 経営者自らによる育休推進メッセージの発信
- 育児参画に関する個別面談の実施(育介法21条の2の個別周知)
- 育休取得者の体験共有ランチミーティング
- 「取らない選択」も尊重することの明確な伝達
実例:従業員70名のD社(IT業)では、社長自らが「育休活用宣言」を行い、男性社員一人ひとりと面談を実施。強制ではなく意向を尊重する姿勢を明確にした結果、自主的な取得者が増加し、取得率70%を達成しています。
中小企業の男性育休推進成功事例
E社(従業員110名 製造業)の成功事例:
「全員が無理なく育児に参画する」を目標に、育休のほか、時短勤務や在宅勤務などの選択肢を用意。業務マニュアルの整備と社内研修で代替要員確保の課題も解決しました。その結果、育休取得率65%、何らかの形での育児参画率95%を達成。社員満足度も向上し、採用面でも好影響が出ています。
まとめ:50~100人規模企業が進めるべき男性育休推進のあり方
育児休業は育児・介護休業法で保障された労働者の権利であり、その行使を強制することは権利侵害となる可能性があります。限られたリソースの中でも、50~100人規模の企業ができることはたくさんあります。
大切なのは、「取りたい人が安心して取れる環境」と「取らない選択も尊重される文化」の両立です。多様な育児参画の形を認め、社員一人ひとりが自分に合った形で育児に関われる職場づくりこそが、中小企業でも実現可能な育休推進策です。
「男性育休100%」という無理な数字にこだわるよりも、「社員が互いに支え合いながら育児に参画できる会社」という現実的な目標に向かって、法的リスクを避けながら着実に前進していきましょう。
【上岡ひとみ経営労務研究所では、50~100人規模の中小企業向けに男性育休取得推進策をご提案しています。限られたリソースでも効果的に育休推進を実現する方法や、助成金活用のノウハウなど、中小企業の実情に合った支援を行っています。お気軽にご相談ください。】