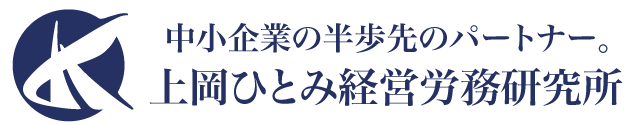同意は不要 給与誤支給・二重払いは通知で回収
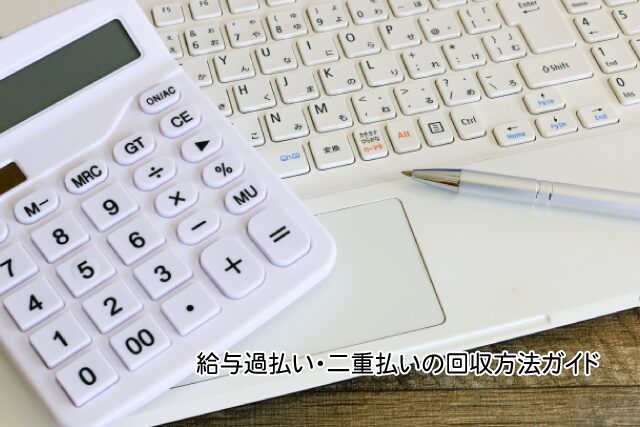
〜法的に守られた「不当利得」回収の鉄則と、やってはいけないこと〜
「家族手当を長期間誤支給していた」
「取引先に誤って請求額を二重払いしてしまった」
—あなたの会社でも、一度は直面したことのある金銭トラブルではないでしょうか。
経理・人事担当者にとって、過払い発覚時の最大の悩みは、「従業員や取引先のごねる交渉に巻き込まれず、どうすれば確実に返金してもらえるのか」という点です。特に従業員の場合、「回収を試みたらユニオンに相談された」「賃金全額払いの原則に違反しないか不安だ」と、対応に及び腰になりがちです。
結論から申し上げます。これらすべての過払金は、法的に会社が強く守られています。
過剰な謝罪や、相手の「合意」を得ようと交渉する必要はありません。
本コラムでは、法的権利(不当利得返還請求権)に基づき、会社が法的に問題なく、かつシンプルに過払金を回収するための二つのケース別に手順を解説します。
1. すべての過払金回収の土台となる「鉄則」
給与・取引先のどちらのケースでも、過払金回収の法的根拠は共通しており、これはすべての回収手続きで従うべきルールです。
基本的な考え方
✓ 通知のみで対応可能(同意は不要)
誤って支払った家族手当を本来の給与額に戻すだけなので、従業員に不利益はありません。
法的根拠
1. 不当利得返還義務(民法第703条)
「法律上の原因なく他人の財産によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において返還する義務を負う」
つまり: 過払い分には返還義務がある。
2. 賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)
本来の給与額に戻すだけなので、この原則には違反しない
2. ケース別:回収手続きの詳細と注意点
【事例1】従業員への給与誤支給(家族手当の誤払いなど)
状況: A社がB従業員に誤って家族手当1万円を9か月間支給。その後、通知なしで毎月1万円を控除したところ、ユニオン加入のB従業員が謝罪を要求。
対応フロー
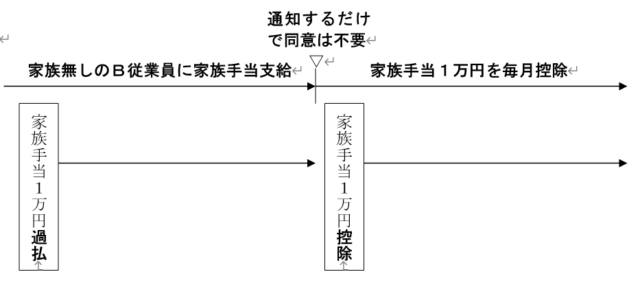
対処方法の詳細
【通知・同意について】
- 事前に控除を通知していなかったことへの謝罪のみ
- 今後の毎月控除について通知(同意取得は不要)
【推奨方法】
- 毎月控除:毎月1万円ずつ控除
- 事前通知は必須、同意は不要
- 本来の給与支給に戻るだけで不利益なし
- 控除額の返金も不要
【やってはいけないこと】
- 一括控除は避ける:毎月少額ずつの控除であれば、従業員への影響が最小限
- 合意を求める:合意を求めると、従業員が拒否した場合に回収できなくなる可能性がある
【事例2】取引先への外注費・仕入代金の二重払いなど
状況: A社が取引先B社に外注費を支払い、その後誤ってもう一度支払ってしまった。(二重払い)。
※この場合も、金銭回収の法的根拠は、【事例1】同様に、「不当利得返還義務(民法第703条) 」の原理が適用される。
対応フロー
- 10日以内に返還 → 利息なし
- 10日超えても返還なし → 悪意の受益者
年3%の利息付き返還義務(民法704条)
対処方法の詳細
【通知・同意について】
- 二重払いが発生したことを取引先に通知し、返還を求める。
- 10日以内に支払うようメール等で通知(同意取得は不要)
【重要ポイント】
- 通知後10日以内に返還しない場合⇒悪意の受益者(民法第704条)
- 年3%の法定利息を付して返還義務
- さらに損害がある場合は賠償責任も
まとめ:トラブルを避けるための最終確認
過払金は「不当利得」として法的に回収権が守られています。淡々と事務的に手続きを進めることが対応策となります。(【事例1】を例に…)
本来の給与額に戻すだけなので、通知さえすれば法的に問題なく対応できます。
✓ やるべきこと
- 事前通知:過払い分を今後控除する旨を明確に伝える
- 謝罪:通知が遅れたことのみ謝罪
✓ 不要なこと
- 従業員の同意取得
- 過払い分の返金
- 過度な謝罪
✓ 法的保護
- 民法第703条:不当利得返還請求権
- 労働基準法第24条:違反にはあたらない
基本的な回収は本ガイドラインで対応可能ですが、貴社の個別の事情がある場合には、別途詳細をお伝えいただく必要がございます。
複雑な事案や、回収が長期化しそうな場合は、法的なリスクを最小限に抑え、円満かつ確実に回収を完了させるため、早期に専門家にご相談されることをおすすめいたします。
ご相談は、下記お問合せフォームをご利用ください。