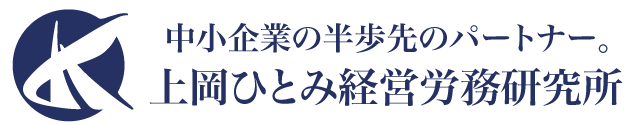【2025年版】社会保険労務士が解説!「調査」の傾向と対策

「調査」の傾向と対策
~年金事務所・労基署・労働局の調査完全ガイド~
登場人物紹介
- 笹川社長(31歳):工務店三代目。アパレル・雑貨・飲食と新事業を次々展開するやり手でITにも強いが、神経質でストレスですぐお腹が痛くなる。
- 佐藤常務(58歳):先々代から笹川工務店を支える経理のエキスパート。大番頭的存在で笹川社長をかわいがっている昭和の人。
- 上岡ひとみ社労士:開業21年のベテラン。230社の顧問先を持つ。笹川工務店の新しい社労士として参画
調査対策の基本は「事前準備」にあります。年金事務所や労働基準監督署による調査は、適正な労働環境維持のための重要な制度です。各機関の調査目的と特徴を理解し、日頃から法令遵守の体制を整えることが、円滑な調査対応の鍵となります。
同業他社で労基署の調査が入った…
 笹川社長
笹川社長笹川社長:
「上岡先生、今日はお忙しい中ありがとうございます。実は最近、同業他社で労基署の調査が入ったって話を聞いて…
システムで労務管理はしっかりやってるつもりなんですが、やっぱり不安で…お腹が痛くなってきた…」
 上岡社労士
上岡社労士上岡社労士:
「笹川社長、ITシステムでの管理は素晴らしいですね!でも調査対応は単なるデータ管理だけでは不十分なんです。まず、調査にはいくつかの種類があることを理解しましょう。」
 佐藤常務
佐藤常務佐藤常務:
「そうですな。私も長年やってきましたが、最近は調査の種類も増えて複雑になってきましたわ。」
 上岡社労士
上岡社労士上岡社労士:
「そうなんです。大きく分けて、年金事務所、労働基準監督署、労働局、そして会計検査院による調査があります。それぞれ目的も処分の重さも違うんです。」
年金事務所調査の最新傾向
 笹川社長
笹川社長「年金事務所の調査って、システムで社会保険の管理してるから大丈夫だと思ってたんですが…」
 上岡社労士
上岡社労士「システム管理は良いスタートですが、最近は調査項目が細かくなっているんです。主に社会保険の適正な加入状況、従業員や役員が正しく健康保険・厚生年金に入っているか、給与額を正しく申告しているかを調べます。」
 佐藤常務
佐藤常務「最近は非常勤の役員さんも対象になるって聞きましたが…」
 上岡社労士
上岡社労士「その通りです!最近の傾向として、非常勤役員でも報酬額や勤務実態によって加入指導されるケースが増えています。複数の事業所から報酬をもらっている場合の合算申告、インフレ手当や年末年始手当などの一時金届出漏れもよく指摘されます。」
 笹川社長
笹川社長「えっ、うちの飲食店とアパレルで役員報酬もらってる場合は?クラウドシステムで管理してるけど、合算って自動でやってくれないんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「まさにそこが盲点なんです!システムは便利ですが、複数事業所の合算申告は手動での確認が必要です。調査で不適正と判断されたら、最長過去2年分の保険料を遡って納付することになります。」
 笹川社長
笹川社長「2年分…うわぁ、お腹が…」
労働基準監督署調査への対策
労働基準監督署の調査は「定期監督」と「申告監督」に大別されます。定期監督は労基署が任意に選定して行う包括的な調査、申告監督は従業員の申告に基づく個別具体的な調査です。どちらも最低賃金法、労働時間管理、安全衛生法の遵守状況が重点的にチェックされます。
 上岡社労士
上岡社労士「次に労働基準監督署ですが、これが一番企業の皆さんが緊張される調査かもしれませんね。」
 笹川社長
笹川社長「やっぱり!勤怠管理システムで労働時間はきちんと把握してるつもりですが…」
 上岡社労士
上岡社労士「システム管理は重要ですが、労基署の調査は3つの分野に分かれます。労働基準法の遵守状況、労働保険料の適正申告、そして労働安全衛生の状況です。」
 佐藤常務
佐藤常務「定期監督と申告監督の違いは何ですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「定期監督は労基署が任意に選んで広く調べるもの、申告監督は従業員からの訴えに基づいて狭く深く調べるものです。申告監督の方が厳しい傾向にあります。」
 笹川社長
笹川社長「申告監督…システムでタイムカードは管理してるけど、従業員が不満を持ってるかもしれない…」
 上岡社労士
上岡社労士「システムだけでなく、実際の運用が重要なんです。36協定の締結、未払い残業代の確認、健康診断の実施状況などが主なチェックポイントです。特に最近は厚生労働省が『過去に重大・悪質な法違反があって改善されていない企業には躊躇なく司法警察権限を行使する』と表明していますから。」
 笹川社長
笹川社長「司法警察権限って…書類送検ですか?お腹が…」
 佐藤常務
佐藤常務「社長、日頃から法令遵守していればシステムも活かせますよ」
労働局・会計検査院による専門調査
 上岡社労士
上岡社労士「労働局では、派遣事業や職業紹介事業の調査、同一労働同一賃金の調査、それから助成金の調査があります。」
 笹川社長
笹川社長「助成金の調査…コロナの時の雇用調整助成金、オンラインで申請したけど大丈夫でしょうか?」
 上岡社労士
上岡社労士「オンライン申請でも調査は同じように行われます。コロナ禍で不正受給した企業や関与した社労士の名前が公表されましたからね。デジタル化が進んでも、助成金の要件確認は特に厳格です。」
 佐藤常務
佐藤常務「会計検査院っていうのもあるんでしたね。」
 上岡社労士
上岡社労士「会計検査院は個別企業を直接調査することはありませんが、他の行政機関を通じて調査します。滅多に当たりませんが、当たれば最も厳格な調査です。労基署や年金事務所の幹部が、会計検査院の職員の前で終始平身低頭だった姿が印象に残ってます(笑)」
調査官による個人差への対応
調査官の個人差も調査結果に影響を与える要因の一つです。しかし、どのような調査官が担当になっても対応できるよう、平時からの法令遵守体制の構築と適切な書類整備が重要です。デジタル化が進む中でも、人による判断要素は依然として大きな要素となっています。
 笹川社長
笹川社長「調査官によって結果が変わるって本当ですか?システムで客観的に管理してても?」
 上岡社労士
上岡社労士「システム管理は客観性を高めますが、最終的な判断は人が行います。正直言って、担当官によってアタリ・ハズレがあるのも特徴なんです。」
 佐藤常務
佐藤常務「どんな方がアタリなんですか?」
 上岡社労士
上岡社労士「経験上、ザックリで優しくて定年が近い男性担当官は、アタリ!逆に細かくて正義感が強く仕事熱心な若い女性担当官は…ハズレと感じることが多いです。」
 笹川社長
笹川社長「でもシステムデータがあれば、客観的に判断してもらえますよね?」
 上岡社労士
上岡社労士「データは重要な武器になりますが、解釈や運用面での判断は調査官次第です。どんな担当官が来ても対応できるよう、日頃からきちんと管理しておくことが大切なんです。」
まとめ
 佐藤常務
佐藤常務「結局、システムも大事だけど、普段からきちんと法令遵守していれば、調査も怖くないということですね。」
 上岡社労士
上岡社労士「その通りです。ITシステムは効率化と正確性を高めますが、それを適切に運用する人の意識が最も重要です。調査は決して企業をいじめるためのものではありません。適正な労働環境を作るためのものです。」
 笹川社長
笹川社長「先生にお任せして良かったです。システムと先生の経験を組み合わせれば最強ですね。でも…やっぱりお腹は痛いままですが…」
 佐藤常務
佐藤常務「社長、胃薬持ってきましょうか?」
 上岡社労士
上岡社労士「笹川社長、ストレス管理も労働安全衛生の一環ですよ。まずは社長ご自身の健康管理から始めましょう(笑)」
上岡社労士からの重要ポイント
調査対応で押さえるべき5つのポイント
- 事前準備が全て:調査通知が来てから慌てるのではなく、日常的な法令遵守体制の構築が重要
- 書類整備の徹底:労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の「法定三帳簿」は常に最新状態で保管
- ITシステムの活用:勤怠管理や給与計算システムは調査対応の強い味方だが、運用ルールの整備も必須
- 従業員とのコミュニケーション:申告監督を防ぐためにも、日頃からの労使関係の良好な維持が大切
- 専門家との連携:社会保険労務士など専門家との密な連携で、法改正への対応と調査リスクの最小化を図る
特に注意すべき最新トレンド
- 非常勤役員の社会保険加入基準の厳格化
- 複数事業所での報酬合算申告の徹底
- 同一労働同一賃金への対応状況
- 助成金の不正受給に対する厳罰化
- 労働安全衛生法違反への司法警察権限の積極的行使
上岡ひとみ社労士事務所より
調査対策・労務管理システムの導入・法令遵守体制の構築でお困りの際は、230社の顧問実績を持つ当事務所にお気軽にご相談ください。デジタル化時代の労務管理を経験豊富な専門家がしっかりサポートいたします。